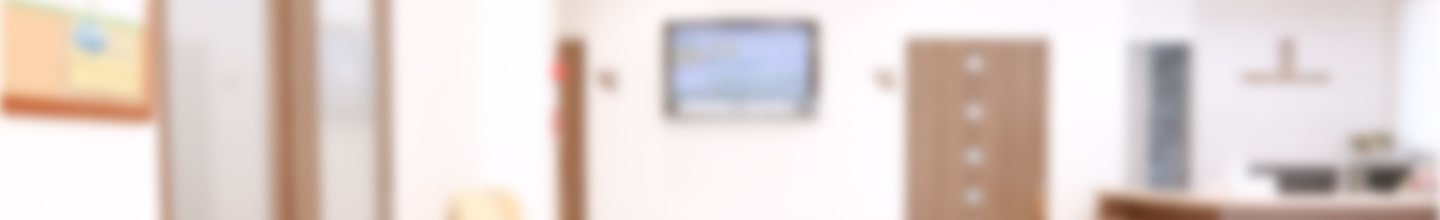高血圧とは
高血圧とは、血管壁にかかる血液の圧力が慢性的に高い状態を指します。一時的に血圧が高いだけで高血圧と診断されるわけではなく、繰り返し測定しても正常値よりも高い場合に高血圧症と診断されます。具体的には、医療機関での測定で最高血圧が140mmHg以上、または最低血圧が90mmHg以上の場合、高血圧と判断されます。ご自宅で測定される場合は、135/85mmHg以上が高血圧の目安となります。
血圧とは、心臓が血液を送り出す際の圧力と、血管がその血液を受け止める際の抵抗によって決まります。心臓が収縮して血液を送り出す時の圧力が「収縮期血圧(上の血圧)」、心臓が拡張して血液をためている時の圧力が「拡張期血圧(下の血圧)」です。これらの数値が示す状態を理解することが、ご自身の心臓の健康管理の第一歩となります。

高血圧を放置することの危険性
高血圧を放置すると、血管や心臓に大きな負担がかかり、様々な合併症を引き起こす可能性があります。血管は常に高い圧力にさらされることで硬く脆くなり(動脈硬化)、血液の流れが悪くなります。
動脈硬化が進行すると、脳梗塞や脳出血といった脳卒中、心筋梗塞や狭心症といった心疾患、腎機能の低下、大動脈瘤、眼底出血などを引き起こすリスクが高まります。また、心臓は高い血圧に打ち勝つために過剰に働き、心臓の筋肉が厚くなる心肥大を引き起こし、最終的には心不全に至ることもあります。高血圧は自覚症状がないまま進行することが多いため、「サイレントキラー(静かなる殺し屋)」とも呼ばれています。
高血圧の診断と治療
高血圧の診断は、診察室での血圧測定を複数回行うことによって確定されます。また、より正確な診断のため、ご自宅での血圧測定も重要です。家庭での血圧測定は、白衣高血圧や仮面高血圧といった、医療機関での測定だけではわからない状態を把握するのに役立ちます。
高血圧の治療は、生活習慣の改善と薬物療法が中心となります。生活習慣の改善には、減塩(1日6g未満)、適度な運動 、禁煙 、節酒 、適切な体重維持 、ストレス管理 などが含まれます。
薬物療法では、患者様の状態に合わせて、様々な種類の降圧薬を適切に選択し、血圧を目標値までコントロールしていきます。目標とする血圧値は、年齢や合併症の有無によって異なりますが、一般的には75歳未満の方で130/80mmHg未満、75歳以上の方で140/90mmHg未満を目指します。ただし、脳血管障害や心疾患、慢性腎臓病、糖尿病などを合併している場合は、より低い目標値となることがあります。
| カテゴリー | 診察室 血圧 |
家庭血圧 |
|---|---|---|
| 75歳未満の方 | < 130/80 | < 125/75 |
| 75歳以上の方 | < 140/90 | < 135/85 |
| 慢性腎臓病(尿蛋白陽性)のある方 | < 130/80 | < 125/75 |
| 糖尿病の方 | < 130/80 | < 125/75 |
| 抗凝固薬の服用中の方 | < 130/80 | < 125/75 |
高血圧において行われる主な検査
高血圧の患者様に対して、血管や心臓の状態を詳しく評価するために、以下の検査を実施しています。
- 血管伸展性検査(PWV)
動脈の硬さを測定する検査です。高血圧が長期間続くと動脈硬化が進行し、血管の柔軟性が失われます。PWV検査によって、動脈硬化の程度を把握し、より適切な治療方針を立てることができます。 - 頚動脈エコー検査
超音波を用いて首の頚動脈の状態を観察する検査です。動脈硬化による血管壁の肥厚やプラーク(血管内のこぶ)の有無などを確認することができ、脳卒中のリスク評価に役立ちます。 - 心エコー検査
超音波を用いて心臓の大きさや動き、弁の状態などを詳しく調べる検査です。高血圧による心肥大や心機能の低下などを早期に発見することができます。 - 尿検査
血圧上昇により、尿蛋白が出現する状態を腎硬化症と呼びます。腎硬化症では、腎臓以外の臓器障害も進行していると考えられ、心筋梗塞や脳卒中などの危険性が高いとされています。
正しい家庭血圧の測定方法
家庭血圧は、高血圧の診断や治療の効果判定に非常に重要です。以下の点に注意して、毎日同じ条件で測定しましょう。
- 血圧計
上腕にカフを巻くタイプの血圧計(上腕カフ型血圧計)を使用します - 測定時間
朝と夜の1日2回、座位で測定します。朝は起床後1時間以内、排尿後、朝食前、降圧薬服用前に測定します。夜は就寝前に測定します。 - 測定環境
静かで過ごしやすい温度の部屋で測定します。 - 測定姿勢
椅子に脚を組まずに腰掛け、カフ(腕帯)の高さと心臓の高さを合わせます。測定中は会話や力を入れたり動いたりすることは避けましょう。 - 測定前
測定前に1〜2分間安静にします。喫煙、飲酒、カフェイン摂取は避けましょう。 - 測定回数
原則として2回測定し、平均値を治療の目安にします。 - 記録
測定した日時と血圧値を血圧手帳などに記録し、医師の診察時に提示しましょう。
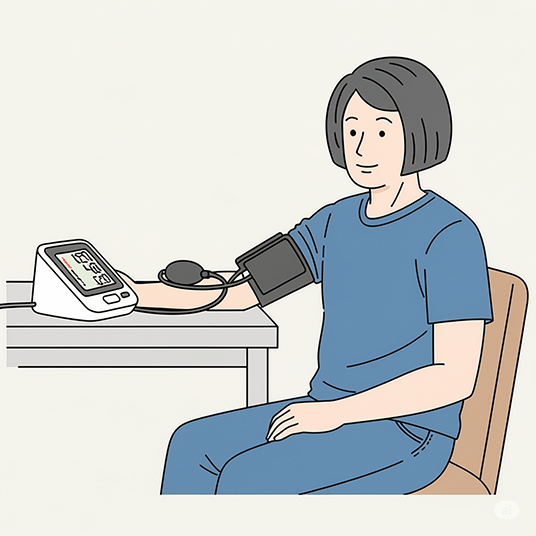
食事療法
高血圧の治療において、食事療法は非常に重要です。特に減塩は最も重要なポイントです。
- 減塩
1日の塩分摂取量を6g未満にすることを目標にしましょう。
漬物、佃煮、干物、練り製品、ハムやソーセージなどの加工品は控えましょう。
汁物や麺類は1日1杯までとし、麺つゆは飲まないようにしましょう。
しょうゆやソースはかけずに小皿に取り、少量をつける、減塩調味料を利用するなどの工夫も有効です。
外食や市販の弁当、惣菜は塩分が多く含まれている場合が多いので、できるだけ頻度を少なくしましょう。 - 野菜・果物
カリウムを多く含む野菜や果物を積極的に摂取しましょう。カリウムは、体内の余分なナトリウムを排出し、血圧を下げる効果があります。ただし、果物の摂りすぎは血糖値や中性脂肪の上昇につながる可能性があるため、主に野菜から摂取することが推奨されます。 - 適切なエネルギー摂取
標準体重を維持するために、適切なエネルギー摂取量を守りましょう。 - アルコール
習慣的な飲酒や過剰な摂取は避けましょう。男性は1日アルコールとして20〜30ml(=日本酒で2合換算)まで、女性はその半分までが適量とされています。 - 禁煙
喫煙は血管を収縮させ、血圧を上昇させるため、禁煙しましょう。